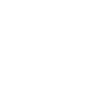第12回
C1グランプリで審査・司会を務めてくださった
町亞聖さんとの充実の対談!
法人や関連企業の取り組みを「伝える力」に昇華する場――それがC1グランプリ。審査員として関わる町亞聖さんと主催者の左理事長が語り合ったのは“言葉にする意義”と“継続の力”。本番を前に、率直で真剣な言葉が交わされた。
〇対談相手
町 亞聖【まち あせい】さん
フリーアナウンサー。医療・福祉分野を中心に取材・執筆・司会を行い、現場の声を伝える活動を続ける。介護イベントや講演の司会も多数担当し、C1グランプリでは前回審査員を、今回は総合司会を務める。著書に『十年介護』(小学館文庫)『受援力』(法研)などがある。

左 敬真【ひだり ひろまさ】 理事長
社会福祉法人千歳会理事長。介護業界の発展と人材育成に尽力し、「C1グランプリ」や「感謝祭」といった企画を通じ、現場の魅力と価値を社会に発信し続けている。

「挑戦」を可視化し、伝える力を育む機会へ

――町亞聖さんには、昨年行われた第3回C1グランプリの最終審査にご参加いただきました。今回はエントリーシートによる第一審査から関わっていますが、各事業所をどのようにご覧になりましたか?
町 はい。今回のC1グランプリでは、エントリシートを初めて採用するとのことでしたので、試行錯誤の跡を感じました。ケアは数値では測れませんので、こちらも何を基準に評価するか非常に悩みました。
左 今回、僕が審査員の先生方にお願いしたのは、ご自身が受けたい介護かどうかを基準に、辛辣に審査してくださいということ。一方で、僕自身はあえて審査に入らなかった。「理事長としての意見」が審査の邪魔になると思ったからです。そういう意味では、審査員の先生方に全幅の信頼を置いて最初から見ていただきました。
――このたびの審査委員には、町さんのほかに、都民ファースト会所属・東京都議会議員の後藤なみさん、『JOINT介護』編集長の青木太志さん、昭和女子大学人間社会学部・福祉社会学科専任講師の熊谷大輔さんにも務めていただいていますね。
町 はい。他のみなさんも審査は大変だったのではと思います。エントリーシートは書くことに慣れていないと、要点がぶれてしまったり、言いたいことがまとまらなかったりするので。
左 今回はテーマを「挑戦」としました。このテーマに沿ってと言っても、なかなか難しかったんじゃないかと思います。
町 まさに皆さんそこに挑戦している印象でした。就職活動でもエントリーシートは使われますが、大事なのは聞かれたいポイントや見せたいポイントだけを書くということ。けれど、今回については「自分たちのやっていることを言語化する」というのが、第一段階だと思うんです。これは、やっていかないと身につきませんので、自分たちのケアを外部に向けて言語化することは、定期的に続けることにも意味があります。
左 今回、審査にエントリーシートを採用したのは、2025年のアーカイブを残す、という意味もありますが、これが今後の財産になるから。例えば、事業所がひとつ増えると70人の職員が増える。成熟してきた組織からまた新しい組織となって、新陳代謝する。そうやって法人の中に1年選手が入ってきたときに、このイズムを伝達するツールにもなるはずです。
町 まさに。言語化することで、それぞれの事業所が育んできた文化を共有することにつながりますね。
――左理事長は3回目となるC1グランプリを、どのような場だとお考えですか?
左 試行錯誤がありながらも、これまで継続をしてきたことで外部に発信しても恥ずかしくないメンバーになってきたなという手応えがあります。
介護の仕事は施設の中で終わらせるのではなく、介護職のメンバーが日々大切している“ダイヤモンド”を、地域に、外の世界に表現豊かにPRしていく必要がある。C1グランプリはその訓練の場でもあるし、他の発表に刺激を受け、気づきの幅広げてもらいたいです。
町 継続的に発表の場があるということが、大切ですね。
左 ええ。そして僕はもう第5回を見据えています。今は千歳会と連携団体という枠組みの中でやっていますが、今後は同業者を巻き込んでいき、この輪をより広めていきたいです。
――町さんは、これまでのC1グランプリをどうご覧になっていますか?
町 退院後に誤嚥性肺炎のリスクがあるからと、医師から禁飲食と言われてしまった利用者さんの食べたいという想いを、訪問歯科や訪問マッサージなど多職種で実現した事例や、ストーマを装着しているという理由で他で入居を断られた方を受け入れ、適切なケアで変わらぬ日常が送れるようした事例が印象に残っています。
左 動画での発表もC1の大きな特徴です。
町 言語化の重要性もありますが、動画での伝わりやすさもあります。例えば外国出身の職員さんたちには、動画のほうが伝わりやすい。
あとは、事例発表は結果だけでなく、どうしたら課題を解決できるか全員で考え実行したプロセスを共有することが大切だと感じています。また、成功事例だけでなく、失敗から学べることもたくさんあります。失敗も共有し、みんなで考えるプロセスにも価値があると思います。
――「伝え方」のお話が出ていますが、千歳会には理念や行動指針、「3つの諦めない」といった強いキーワードが職員に根付いています。
町 食べる喜びを諦めない、旅行する喜びを諦めない、社会との接点を諦めない、という「3つの諦めない」ですよね。私も母の介護で心がけていたことです。
左 これらは長い時間をかけて、チームとともに練り上げてきた言葉たちです。最初に生まれた言葉は、自分たちの強みや今回の「挑戦」を考える基盤になるはず。それは一人の職員が頑張っただけで終わらせるのではなく、法人や関連企業全体で伸ばしていくこと。だからこそ、僕はC1をしくみ化してメソッドをつくりたいんです。
町 なるほど。メソッドをつくるには、共有することが第一歩だと思います。例えば、「旅行する喜びを諦めない」にしても、できていないところは初めからできない言い訳や理由を探してしまうことが少なくないんですよね。不可能を可能にした事例を共有し、可能にしたプロセスを一つひとつ分解していくと、それがメソッドになります。
まずはできることからで良いと思います。「うちもやってみよう」という、挑戦の第一歩を踏み出してほしいです。
――今後のC1グランプリに期待することは?
左 やってよかったねで終わりにしてほしくないですね。今回のC1で何を持って帰ったの? 来年はどんな企画をあげるの? ここから予算をとって、事業所独自でなにか勉強会なりイベントを企画してもいい。とにかく、このC1の機会を「きっかけ」にしてほしいですね。
町 私は、医療関係者にもぜひC1を見に来てもらいたいと思います。長年、医療介護業界を取材してきましたが、まだ医療と介護の間には壁が立ちはだかっていると感じます。在宅の現場ではだいぶ医療と介護の連携が進んできましたが、残念ながら病気だけを診ている病院の医師は少なくありません。暮らしを支え、生きることに伴走する介護職の実践を、そんな先生方に見てもらいたい。医療には限界がありますが、ケアの可能性は無限だということを再確認させてくれるC1グランプリを今年も楽しみにしています。
――ありがとうございます! 町さんは引き続き、会場での審査もよろしくお願いします。

(注釈)
『C1グランプリガイドブック』のために収録した「スペシャル対談」を再掲載しました。
(お知らせ)
今回対談いただいた町亞聖さんの著書については、こちらをご覧ください★