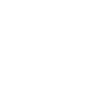こんにちは、デイサービスセンターちとせです。
私たちが目指すのは、「いつまでも自分らしく、元気に活動できる毎日」。
そのためには、ご自身の健康状態を正しく知り、早めの対策を講じることが大切です。
今回は、近年注目されている「フレイル(虚弱)」をテーマに、
全3回に渡り、健康寿命を延ばすための具体的な行動について、
理学療法士の視点から分かりやすくお伝えします。
1回目の今日は「フレイルって何だろう?」です。
 フレイルって何だろう?
フレイルって何だろう?
「フレイル」とは、健康な状態から要介護状態へ移行するまでの、
心身の活力(筋力や心、認知機能など)が低下している状態を指します。日本語では「虚弱」と訳されます。

病気ではないけれど、「最近疲れやすいな」「歩くのが遅くなったな」と感じる、
健康と要介護の間の、ちょうど「黄信号」の状態です。
このフレイルには、「可逆性」という大切な特徴があります。
つまり、早めに気づいて適切な対策をすれば、健康な状態に戻る可能性があるということです。

フレイルを放置すると、ちょっとした病気や怪我がきっかけで
一気に要介護状態に進んでしまうリスクが高まります。
だからこそ、日頃からの予防と対策が非常に重要になるのです。

フレイルは、単なる体の問題だけでなく、以下の3つの側面から構成されています。
1. 身体的フレイル(フィジカルフレイル)
• 筋力や移動機能の低下:歩く速度が遅くなる、疲れやすい、ペットボトルの蓋が開けにくいなど。
• サルコペニア(筋肉量・筋力の減少)やロコモティブシンドローム(運動器の衰え)などが代表例です。
• 最近では、口腔機能の低下を指すオーラルフレイルも注目されています。

2. 精神・心理的フレイル
• 認知機能の低下:物忘れが多くなる、軽度の認知症。
• 気分の落ち込み:うつ状態、やる気の低下。

3. 社会的フレイル
• 社会との交流の減少:外出の機会が減る、独居、友人や家族との会話が少なくなる。
• 経済的な困窮。

これらの状態は、適切な対策を行うことで予防や改善(可逆性)が可能である点が重要視されています。
次回は、「フレイル予防の3つの柱:三位一体で健康寿命を延ばす」です
お楽しみに!